最澄が中国から持ち帰った茶を比叡山の麓に植えた、という伝説。安土桃山時代に書かれた「日吉社神道秘密記」(1582年、祝部行丸 著)に記録があると聞くので、調べてみました。
「日吉社神道秘密記」の茶の記録

茶の本やサイトでは、日吉大社の伝承をまとめた書物「日吉社神道秘密記」(1582年、祝部行丸 撰)に、
- 805年、最澄が唐より茶の種を持ち帰った
- 比叡山のふもと(現在の大津市坂本地区「日吉大社」あたり)に茶の木を植え、栽培した
と記録されている、という記述をよく見かけます。そこで、出典を調査してみました。この書物は、最澄の時代から700年以上後に執筆されたものなので、信ぴょう性については一抹の不安が残るものではあります。
国史「群書類従」の収録内容
「日吉社神道秘密記」は、日吉大社の禰宜である祝部行丸が、安土桃山時代に著した書物です。原本は確認できませんでしたが、国史の一大叢書「群書類従 第壹輯」(経済雑誌社 1893-1894年)に収録されていました。
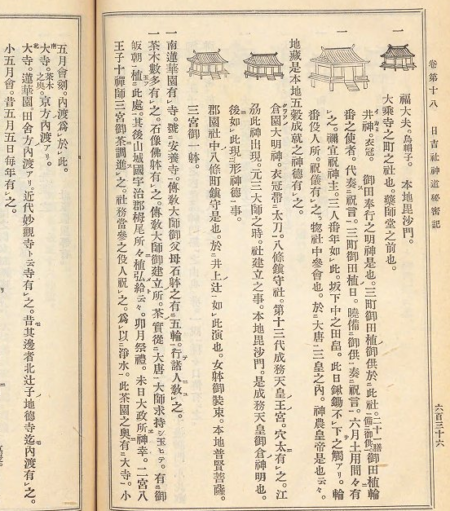
茶木數多 之有り。石像仏体 之有り。伝教大師(=最澄)御建立の所。茶の賓 大唐従い、大師 求持し玉ひて。御皈朝有 此處 植え玉う。其後、山城国宇治郡梶尾 所々に、植弘め給と 云々。
卯月祭礼。未日大政所へ神幸。二宮・八王子・ 十禅師・三宮に、御茶に調之進す。社務富参之役人 之祝う。浄水を以て為す。此茶園之奥に大寺有り。小五月会刻。内渡此於為。
「群書類 従第壹輯」(経済雑誌社 1893-1894)の「日吉社神道秘密記」の章より

ここから読み解けることは、
- 茶の木が数多くあった
- 最澄が唐から茶を持ち帰り植え、宇治や梶尾にも広めた
- 卯月末日に祭礼があり、日吉大社の各社(二宮・八王子・十禅師・三宮)に茶を献じた
- 茶園の奥には、大寺があった
ということで、茶を植えた具体的な時期や場所は、分かりませんでした。
茶の歴史としては、「宇治や梶尾に茶を広めたのは、鎌倉時代の栄西」というのが通念です。それより前に最澄が広めたというのは、検証の余地があります。ただ、この時代、嵯峨天皇が各地に茶の栽培を命じていますし、各地で茶が栽培されていてもおかしくはありません。
日吉社神道秘密記(写し)の内容

尚、愛知県の西尾市立図書館所蔵の「日吉社神道秘密記」の写しは、「群書類 従第壹輯」の収録内容とは若干内容が異なっていました。
茶園の事
歳毎の卯月末の日、二の宮・八王子・十禅師・三官に、浄水を以て煮茶、奉調進し也。
非古法、伝教渡る唐の之砌(?)、茶の賓 持め、而 皈朝す 之時始、此の園に植也、宇治 梶尾 次けり。
日吉社神道秘密記(祝部行丸、1587年)(写し)※出典:西尾市立図書館
「群書類従 第壹輯」と同じく、
- 卯月末日に祭礼があり、日吉大社の各社に茶を献じた
- 最澄が唐から茶を持ち帰り、この園に植えた
- 他に、宇治や梶尾にも広めた
という記述があるほか、「日吉社神道秘密記」には、「毎年5月末日(陰暦4月)に日吉茶園の茶を煮て、献茶をしていた」ことも書かれています。写しですので、後世に書かれたことを考慮する必要があります。これ以外にも寺社の記録を辿っていくと、茶の歴史認識が大きく変わるかもしれません。
日吉大社の中興の祖「祝部行丸」
そもそも「日吉社神道秘密記」の執筆者である祝部行丸(はふりべゆきまる)は、どういう人物なのか。
室町~安土桃山時代の日吉社の社家に生まれ、名は生源寺行丸(1512-1592年)。日吉社社家の始祖・琴御館(ことのみたち)宇志丸の37代で、生源寺行貫の子。「日吉大社の中興の祖」と呼ばれているそうです。
元亀2年(1571年)、織田信長の比叡山焼き討ちによって、日吉社は焼失。行丸は、朝廷に日吉社再建を願い出るなど、復興に尽力します。
1582年の「本能寺の変」の後、天正11年(1583年)に復興を開始。灰燼と化した日吉社は再建を遂げました。祝部行丸は復興に当たり、日吉社に関する数多くの記録を残しており、焼失前の日吉大社の状況や謂れなどを「日吉社神道秘密記」に書き記しています。滋賀県大津市にある「聖衆来迎寺」「八戸神社」にお墓があります。
茶を献じた日吉大社の各社

日吉大社で茶を献じられた社として、夫婦神を祀る「二宮・八王子・十禅師・三宮」の東本宮系の4社が、記載されています。
山を御神体とする神社の場合、山上にある社を「奥宮」(山宮とも言う)、山の麓にある祭場を「里宮」と呼ぶそうです。「日吉社神道秘密記」の記録によれば、この奥宮と里宮に茶が献じられていました。
信仰の原点である地元神への献茶
奥宮と里宮の祭神は同一で、「奥宮」に荒魂、「里宮」に和魂が祀られています。地主神の「大山咋神」とその妻「鴨玉依姫神」に茶を献じていた、ということになります。
| 旧社名 | 現社名 | 祭神 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 八王子 | 牛尾宮 | 大山咋神 荒魂 | 地主神(比叡山に宿る山の神)。牛尾山の奥宮にある |
| 三宮 | 三宮宮 | 鴨玉依姫神 荒魂 | 大山咋神の后神。牛尾山の奥宮にある |
| 二宮 | 東本宮 | 大山咋神 和魂 | 牛尾宮の里宮。 |
| 十禅師 | 樹下宮 | 鴨玉依姫神 和魂 | 三宮宮の里宮。霊泉の井戸があり、昔は神水を取っていた |

東本宮の「亀井の霊水」
東本宮には「亀井の霊水」という、伝教大師ゆかりの井戸があります。
昔ここには池があり、伝教大師 最澄が参拝した際、霊亀が現れたことから、占いにより閼伽井(※)とし「亀井」と名付けたと言います。亀甲のように六角形に石が組まれています。
※閼伽井:仏前に供える水を汲むための井戸。
また、亀井は、明治時代の名所案内「東海道名所図会」で、「茶をいれるのによい」と紹介されています。
亀井
二の宮の傍にあり。伝教大師存在の時、霊亀この井より現れしより名とす。 水極めて清冽、味わい甘軽、茶を爚るに可なり。
東海道名所図会(明治43年、秋里籬島 編)
亀井の霊水は汲むことはできませんが、東本宮の後方には清水が湧き出ており、こちらは汲んで飲むことができます。